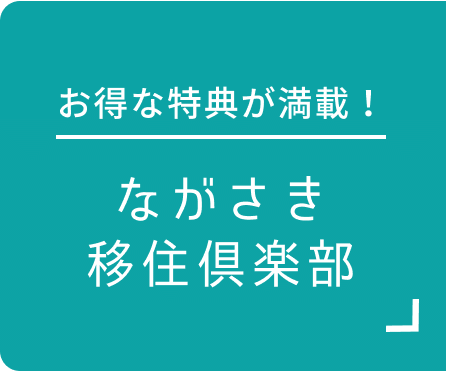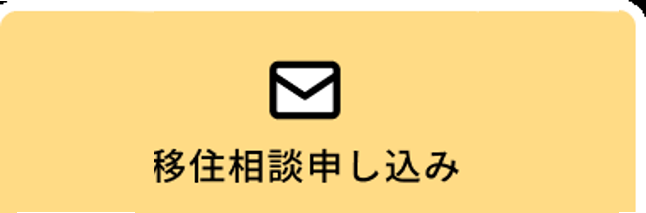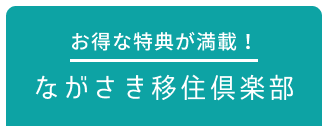-1024x550.jpg)
- 移住年
- 2016年
- 職業
- 自営業
東京で長年キャリアを積んできた齊藤晶子さんが、人生の折り返し地点で選んだのは、静かな海と山に囲まれた長崎県東彼杵(ひがしそのぎ)町での暮らし、そして民宿という新たな挑戦でした。都会の利便性と引き換えに失われがちな人との距離感。そこから一歩離れ、地域とともに生きる道を見出した彼女の物語には、現代を生きる多くの人にとって人生を豊かにするためのヒントが詰まっています。
「いつか海の近くで暮らしたい」─東京から東彼杵町へ
大学卒業後、齊藤さんは外資系のIT企業に新卒で就職。以降も複数の企業でキャリアを重ね、東京で働き続けました。仕事はデスクワーク中心で、パソコンに向かう日々。刺激的な環境である一方で、隣人の顔も知らない生活に、どこか寂しさを感じていたといいます。
また齊藤さんは学生時代、ヨット部に所属し湘南の海で活動していた経験もあり「いつか海の近くで暮らしたい」という思いを心の奥にずっと抱えていました。
そこで50歳を目前に移住を決意し、思い切って早期退職を決断。夫が関西出身だったこともあり、移住先候補の四国や九州をめぐる“暮らし探しの旅”をはじめました。長崎県との出会いは偶然のようで、どこか必然でもありました。知人の勧め、そして移住検討者向けにキャンピングカーを貸し出す長崎県のユニークな取り組みをきっかけに、実際に東彼杵町を訪れることになります。本屋でたまたま手に取った雑誌の表紙に載っていた千綿駅の美しい風景──その小さな駅舎と海辺の景色に、心を掴まれたことも、東彼杵町への移住を後押しした理由のひとつでした。

「便利な田舎」ではじめた、まちぐるみの“おもてなし”
初めての地方暮らし。それが東彼杵町だったということは、齊藤さんにとって幸運だったのかもしれません。それは、道の駅や図書館、スーパー、ジムといった施設が町に揃っていて、車で少し足を延ばせば温泉地や空港にも行けるという、まさに「便利な田舎」だったから。
そこで齊藤さんが始めたのは、民宿「さいとう宿場」。「終電を気にせずに飲める場所があったら」というシンプルだけれど切実な、元都市生活者としての発想から生まれたものでした。
宿では、チェックインの時にゲストの旅の目的や好みを聞きながら、一人ひとりに合わせて地元のお店や過ごし方を提案しています。まるでコンシェルジュのようなそのスタイルは、齊藤さんのやりたかったこと。しかし彼女一人の力でできるわけではありません。地域のお茶屋さんや雑貨店、飲食店と手を取り合いながら「まちぐるみ」での“おもてなし”を実現しているのです。

「あるものを楽しむ」──東京にはない、日々の豊かさ
移住してまず驚かされたのは、スーパーマーケットに並ぶクジラの肉でした。年末年始などお祝いの席には「鉢盛り」と呼ばれる郷土料理にクジラが入るのがご馳走、という文化に触れ、東京との違いを面白く感じたといいます。
一面に広がる茶畑もまた、この町を彩る風景に欠かせません。特産である彼杵茶、その収穫の時期になると、町全体がその香りに包まれるような感覚があるそうです。
季節が変われば、海の色も空の表情も変わる。ある朝には青く広がる海を眺め、ある夕暮れには虹を見上げる。ときに海上に大きなアーチを描く虹は、言葉にならない美しさだといいます。
そんな日々変化する自然や町の風景、そして地域の人たちとの穏やかな関わり。東京では感じることのなかった「変化のある日常」が、齊藤さんの暮らしを彩っています。
地域には挑戦を応援する空気が流れており、カフェなど新しいお店が次々とオープンしています。そのような移住者が馴染みやすい環境があるからこそ、齊藤さん自身も自然と起業の一歩を踏み出せたのかもしれません。

会話が“はじまり”になる──体験としての宿泊
「うちには、誰かと話したい人が泊まりに来ると思っています」と齊藤さんは笑います。その言葉通り、この宿はただの寝泊まりの場ではなく、旅行者と地域、そして日常と非日常をつなぐ小さなハブになっています。
春はお茶摘み、夏は釣り…など「この季節にはこれ」という旅行者にとっては非日常の楽しみが溢れています。
お客様一人ひとりから、旅の目的や過ごし方の希望を丁寧に聞き取り、その人らしい時間を一緒に考え提案する。そんな「まちぐるみ」の“おもてなし”は、ひとつの“共創”といえるかもしれません。
都市での暮らしに慣れた人ほど、ここで感じる“距離の近さ”や“季節との調和”に、驚きを覚えることでしょう。「まずは一度、泊まりに来て体験してみてください」──それが齊藤さんの静かな招きの言葉です。