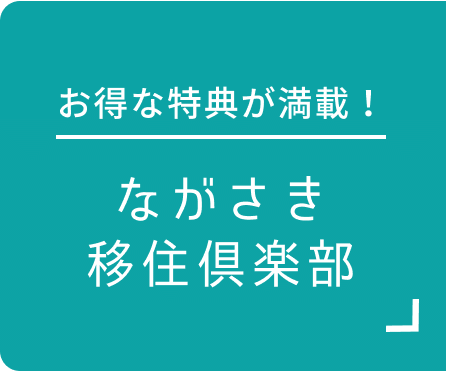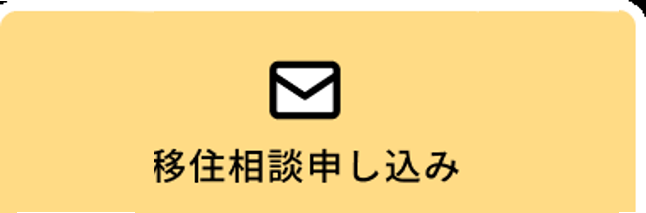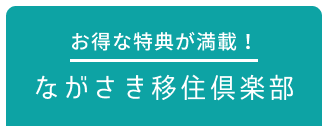- 移住年
- 2015年
- 職業
- 自営業
「島原を出たくてしょうがなかった」——そう語る佐々木翔さんは、建築家として福岡や東京での暮らしを経験したのち、30歳で地元・島原(しまばら)市へUターン。移住前に島原での2年間のリモートワークを経て、「自然とのつながり」や「暮らしの豊かさ」に気づき、現在は島原市で設計事務所を営んでいます。今回は、建築家として島原の未来に挑む佐々木さんの姿と、湧水(わきみず)に恵まれたこのまちの魅力をお届けします。
「出たくてしょうがなかった」18歳の自分が見た島原
「18歳までは、この街を出たくてしょうがなかったんです」。そう語るのは、長崎県島原市出身で建築家としてUターン移住を果たした佐々木翔さんです。
「何もない場所だと思っていたし、海から熊本や福岡の大牟田あたりまで見えていたので、あの海の向こうまで行ってみたいと。高校生の頃、自転車で帰りながらずっと思っていました」。
大学・大学院は福岡、その後は東京の設計事務所で働きました。都会での暮らしは楽しかったけど、帰省するたびに感じる故郷の魅力が、佐々木さんの心を少しずつ動かしていきました。
「たまに帰ってくると、島原も実はいいところなんだなと感じることができたんです。意外と普通に暮らせると気づいたし、自然環境はとても豊か。昔と変わらない自然と人との関係、暮らしぶりをみて、すごく良い街だと思うようになりましたね。」

島原にいてもできた東京の仕事―Uターンを決意
30歳で島原にUターンした佐々木さんは、父の設計事務所「INTER MEDIA」を引き継ぎ、地元で自身の設計事務所として再スタートを切りました。
移住する前は東京の企業に在籍しながらも、福岡や佐賀の嬉野の公共施設の仕事を担当していました。
(辞める前の)最後の2年間はリモートでの仕事も多かったですが、九州の仕事ばかりだったので、実家の事務所でちょっと作業したり、SKYPE(オンライン通話アプリ)で東京の上司と話したりしながら、現場に通うというようなことをやっていたんですよ。
ここでの生活は相当不便だと思っていたけど、リモートで仕事もできるし、光回線も整備されていてネットのスピードも早かったので、島原でもやれると感じました。」
「当初は島原に帰るつもりはなくて、福岡か東京で独立して設計事務所をやろうと思っていました。ところが、島原で仕事をしていた2年間で『ここでもやっていけるのでは?』と思って。同じ仕事ができるなら、島原で展開できる方が面白そうだし、建築家があまりいない土地で貢献できることも大きいと考えました」

湧き水とともにある暮らしと文化
島原の象徴とも言えるのが、街中に豊かに湧き出す「湧水」です。
この水の存在に魅せられた佐々木さんは、築175年の古民家に構える自身のオフィスに「水脈」と書いて「mio」(ミオ)という名前をつけました。
水と人の流れはどこか似ていると言います。
「淀(よど)んだり溜まったりしつつ、様々な学びや知見を交流しながら、それぞれの場所に流れて帰っていく。学びや知見を共有して、交流する。そしてまたそれぞれの場所に流れて帰っていく。そういう循環のある場所にしたいと思いました」
「そんな場所になってほしいという思いで、水脈=mioと名付けました。島原の文化そのものを表せたらいいなと思って。」
市内には1日に何千トンもの水が湧き出る水脈が点在し、まちなかを清らかな水が流れています。その水は、生活の中にも当たり前のように溶け込んでいます。
「mioの室内にも湧き水の水路があるんですよ。元々は泥つき野菜を洗ったり、ジュースを冷やしたり。生活の道具として水が活かされてきた文化が残っているんです」と佐々木さん。
近くの湧き水から汲んだ水を飲んで、「これが当たり前にあるって、すごいことですよね」と笑います。
こうした文化と自然のつながりは、人の暮らしと深く結びついています。「島原には、人の手では作れない“本物”がたくさん残っている。それとともに暮らすことが、大きな価値になる」と語ってくれました。

熊本を望む生活圏
島原市は熊本市内へのアクセスも良好。フェリーを使えば30分で熊本に渡ることができ、市内中心部にもすぐ行けるのだとか。
「熊本に日帰りでいけちゃうんですよ。熊本市内のアーケードに高校生の時に日帰りで行ってました。長崎市内に行くより近いし、安い。船で30分で熊本に着いて、そこから20分くらいで市内中心部に着くんですよ」
有明海に面した島原市だけに、近隣の熊本県へのアクセスの良さも大きな魅力の一つかもしれません。
建築を通して、これからの“豊かさ”をつくっていく
人口減少が進むなか、地域の未来をどう描くのか。佐々木さんは「島原や長崎の人口はどんどん減っていっていますが、減ること自体は僕はネガティブだと思っていないです。緩やかな衰退の中でも、豊かに暮らしていけると思っています」と語ります。
「僕は建築の仕事をしているので、人が集まる場を作ること、そしてそのためには何が必要かを考えることに、専門家として携わることができると思っています。長崎や島原で豊かに暮らしていくための貢献ができればと思っています。」
自然、歴史、人、そして暮らし。島原には、都会では得られない“アタリマエ”が残されています。そしてその“アタリマエ”こそが、これからの時代を豊かに生きるヒントになるのかもしれません。
「水の音を聞きながら過ごす日常って、すごく気持ちがいいんですよ」。
そう語る佐々木さんのまなざしの先には、地元とともに歩むこれからの未来が広がっていました。